以前は「育休は女性が取るもの」という考えが強かったですが、子育てをしやすい環境の整備のため、2022年には育休制度の改正が行われ、男性でも育休が取得しやすくなりました。また、近年の働き方改革やワークライフバランスを重視する風潮からも、男性が育休を取得することは、より一般的になってきたのではないかと思います。
赤ちゃんの誕生を機に、育休を取得しようと思っている方の中には、「育休を取得するメリットはなんとなく想像できるけど、育休を取得するデメリットはどんなものがあるんだろう?」という疑問を抱えている方もいるかと思います。
この記事では、これまでに15ヶ月の育休期間を過ごした経験から、「男性が育休を取得するメリット・デメリット」について解説していきます。
皆さんの育休を取得する際の参考になれば幸いです。
育休を取得するメリット
子育てに積極的に関わることができる
赤ちゃんのお世話について、育休を取得していないと、平日はママが中心になりがちですが、育休を取得していれば、日々の育児に積極的に関わることができます。

1番に思いつくメリットはこれだね。
育児をするための休業だから、おむつ替え・離乳食・お風呂・寝かしつけ・一緒に遊ぶなど、授乳以外の育児はパパが主体的に行おう。
子どもと共に過ごす時間を確保できる
普段の生活では、平日は朝の7時30分に家を出て、帰って来るのは夜の8時過ぎで赤ちゃんの起きている時間に家にいないなんてこともあるかと思います。
育休を取得していれば、子どもと過ごす時間を確保し、子どもの成長を見守ることができます。

生後5ヶ月の娘の場合は、朝7時頃に起床して、夕方6時にお風呂に入り、夜の9時前には就寝するというリズムで生活しているよ。
育休を取得していないと、平日は育児どころか赤ちゃんを抱っこする時間もないなんていう日も出てきてしまうかもね…
父親としての自覚を持ちやすくなる
育休を取得して積極的に育児に参加をすることは、パパと赤ちゃんとの関係性を深め、親としての役割を実感でき、父親としての自覚を持ちやすくなります。
妻の負担が減る
パパが育休を取得することで、ママと育児や家事の分担ができ、ママの負担を減らすことができます。特に、出産直後はママの身体的負担が大きく、精神的にも不安的になりやすい時期であるため、パパの育休取得により、ママの負担を軽減することが重要です。

産後うつの発症率は10〜15%程度と言われているんだって。
出産直後のパパの育児参加は、産後うつの防止にもつながるみたい。
夫婦で助け合える
夫婦で育休を取得することで、育児や家事を分担でき、睡眠時間の確保や自分の時間を持つことができるので、心にゆとりを持って赤ちゃんと接することができます。
また、赤ちゃんを育てていく上での不安を夫婦で理解し合い、協力して乗り越えて行くことができます。

楽しく赤ちゃんと接するためにも、自分の時間を持って気分転換をできるのは大事だね。
ママも初めての子育てで悩むこともたくさんあると思うから、一緒に育児をして悩みや不安を共有できると精神的な不安も軽くなると思うよ。
妻のキャリアロス期間を短縮できる
育休を取得して、パパが育児に積極的に参加する習慣が身につけば、パパの復職後もママの負担が軽減されます。ママが育児と仕事の両立をしたいと考えている場合、復職の時期を早められるなど、育休中のキャリアロス期間を短縮することも可能です。

育児と仕事の両立には夫婦の協力が必要だね。
育児休業給付金を受給できる
雇用保険に加入している会社員や共済組合に加入している公務員の場合は、「育児休業給付金」が支給されます。育児休業給付金の支給額は、最初の6ヶ月が休業開始時賃金の67%、それ以降は50%です。
給付金には所得税や社会保険料がかからないため、実際の手取り額と比較すると、最初の6ヶ月は育休前の約80%、それ以降は約60%となります。
さらに、2025年4月以降は両親がぞれぞれ14日以上育休を取得すると28日間は「育児休業給付金」の給付率が80%に引き上げられ、育休前手取り額の100%相当が支給される計算となります。

育児休業給付金はパパ・ママそれぞれが支給の対象だから、毎月どれくらいの支給がされるか計算しておこう。
シュミレーションには、以下のサイトがオススメだよ。
ママ・パパの産休育休の 期間と金額を自動計算します。(社会保険労務士法人アールワン)
育休中はどうなる? 収入シミュレーション(日立ハイテク)
社会保険料免除制度を利用できる
「育休を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月まで」の期間は社会保険料が免除されます。また、ボーナスについても、ボーナス月の月末が育休期間に含まれていれば、社会保険料が免除されます。
【リーフレット】育児休業等期間中の 社会保険料免除要件が見直されます。(厚生労働省、日本年金機構)
社会保険料の免除によって、将来の年金は減りませんし、医療も従来通り3割負担で受診ができるので、安心です。

社会保険料の負担は大きいから、育休の開始日や終了日によって10万円程度の負担の有無が変わることも珍しくないよ。特に育休の開始・終了がボーナスの月と被る人は要チェックだね。
住民税非課税世帯になる可能性がある
先に解説したとおり育休中は給料は支給されず、代わりに「育児休業給付金」が支給されます。「育児休業給付金」は非課税であるため、夫婦の育休開始時期や終了時期によっては、住民税非課税世帯になる可能性があります。住民税非課税世帯に該当すると、様々な給付金の対象になることや2歳児までも保育料が無料になるなど行政からの手厚い支援を受けることができます。

夫婦共働きで給与所得のみの場合の住民税非課税世帯の目安は、1/1〜12/31までの収入が、夫婦それぞれ100万円以下となりますが、詳しくは市区町村の税務課に確認しよう。家族と税(国税庁)
保育料は3歳児以降は無料だけど、2歳児までは所得や市町村によっては月5万円程度かかることも。これが1年間は無料になるのはありがたいね。
第2子を検討する余裕が出てくる
2人目の子どもを諦める理由は、「経済的な理由」や「年齢・体力的な理由」もあげられますが、「育児のストレスや負担」や「ママの仕事と育児の両立」という子育ての大変さが起因している理由もあります。
パパが育休を取得することで、「ママの育児負担の軽減」や「復職後も夫婦で協力して育児をする体制」が構築されれば第2子以降を検討する余裕が出てくることにつながります。
育児経験が視野を広げる
育児をしていると予期しないことが起きたり、子どもへの対応に試行錯誤し、反省と改善を繰り返すことも多くあります。子育てをしていくなかで、責任感の向上や周囲への思いやりのこころなど、親自身も成長していくことができます。

「育児」は「育自」とも言われているんだって。子育てをとおして親自身も人間的に成長していけるといいね。
職場の業務体制の見直しにつながる
育休取得によって、これまで自分の担っていた仕事は一旦周囲に引き継ぐケースが多いかと思います。周囲に引き継ぐ際に、業務の洗い出しが行われ、属人化が解消されるなど仕事の標準化や効率化が進む可能性が期待できます。
他にも、育休を取得する男性が増えることによって男女問わず育児を支援する環境が整うことが期待できます。
まとまった時間を作ることができる
夫婦で育休を取得すればまとまった時間を作ることもできます。この時間を活用してスキルアップのための勉強をしたり、スポーツジムに通ったり、働いていては時間が足りなくてできないことにもチャレンジすることができます。

第1子の場合は特に時間を作りやすいよ。第2子以降で上の子がまだ手のかかる年齢の場合は、育休中でも自分の時間を作るのは難しいことも。
育休を取得するデメリット
給与は無給になり、家計全体の収入が減る
「育児休業給付金」は支給されますが、今までの給料収入よりは減ってしまいます。育休を取得する前に家計の見直しや、育休中の収支シュミレーションを行う必要があります。
| パパ(休業前との差額) | ママ(休業前との差額) | 合計(休業前との差額) | |
| 育休前(手取り月収) | 250,000円 | 200,000円 | 450,000円 |
| 育休中(6ヶ月まで) | 200,000円(-50,000円) | 160,000円(-40,000円) | 360,000円(-90,000円) |
| 育休中(6ヶ月以降) | 150,000円(-100,000円) | 120,000円(-80,000円) | 270,000円(-180,000円) |

夫婦で育休を1年間取得した場合は、毎月の収入減分(9万円×6月+18万円×6月=162万)に加えて、ボーナス(夫80万円/年、妻60万円/年)がなくなるのを合わせると年間の収入が300万円以上減ることも考えられるよ。
赤ちゃんにかかる出費も増えるので、育休の期間については事前に夫婦での話し合いが必要だね。
住民税の支払いが来る
会社員・公務員の場合、住民税は給料から天引きされますが、育休に入ると給料天引きができなくなるため、直接支払う必要があります。もともと払う必要があるものですので、デメリットではないですが、想定外の支出で慌てないようにしましょう。

住民税は昨年の所得に課税されるから育休を取得しても支払う必要があるよ。育休を取得して所得が減った分、次年度は住民税が安くなるよ。
育休開始の時期にもよるけど、6月から育休を取得した場合、1年分の住民税が給料天引きできないため、これまでの手取りの1ヶ月分ほどの請求が来ることもあるみたい。
同僚への仕事の負担が増える可能性がある
育休を取得すると、自分が担当していた仕事を外のメンバーでカバーする必要があり、負担が増加します。代替人員を確保できた場合でも、教育に時間を割かれるなど周囲に負担をかけます。

周りの負担が増えることは避けられないと思うよ。その負担を少しでも軽減するために育休前に業務内容を整理し、マニュアルを作成し、丁寧な引き継ぎを行おう。
育休取得のメリットの部分でも説明したように、育休の取得を機に業務効率化が行われたり、育児を支援する環境が整うと理想だね。
復職する時に不安になる
長期間の育休を取得すると、仕事に対するブランクができ、復職後すぐに仕事の感覚を取り戻せるかや、自分の能力が落ちていないか不安に思う場合があります。また、業界に関する情報が入りづらいので、育休取得によって情報の不足やシステムなどの環境の変化へに対応できるか不安に思う可能性があります。

長期の育休の場合は、時間を見つけてスキルアップのための学習を行うことで不安を軽減できると思うよ。
僕も普段はデスクワークだから、ブログの更新を通してパソコンを触ることを意識しているよ。
出世に影響するのでは?という懸念がある
本来あってはならないことですが、育休を取得することで職場での評価が下がったり、復職後に「誰にでもできる仕事」や「替えのきく仕事」に回されることで、出世が遅れるのではという懸念が出る可能性があります。
ハラスメントの懸念がある
上記と被る内容ですが、育休や時短勤務の取得を希望した際に、上司や同僚から嫌がらせなどを受ける懸念が出る可能性があります。
妻のストレスが溜まる
パパが育休を取得しても家事や育児に参加せず、自分の趣味や友達との付き合いを優先してしまう「とるだけ育休」の場合にはママのストレスが溜まる原因になります。

赤ちゃんの誕生によりパパへの愛情が下がるのは必然だけど、パパが一緒に子育てをした場合はパパへの愛情も徐々に回復していくんだって!
パパの育児と愛情曲線!?(東京都)
人間関係が狭まる
育休中はママや赤ちゃんとのコミュニケーションがメインとなり、仕事関係の人との接点が少なくなります。その一方で、地域の子育て支援センターなどで同い年の子どもを持つパパ友など新たな人間関係の形成も期待できます。
まとめ
以上、男性が育休を取得するメリット・デメリットについて解説してきました。
育休を取得するメリットについては、何と言っても「子育てに関わり、子どもと過ごす時間を持つことができる」ことです。子どもの成長はとても早く、赤ちゃんの間の成長を間近で見守ることができる時間はかけがえのないものになると思います。
その一方で、赤ちゃんの誕生により養育費などの支出が増える中での育休取得による収入減というのは大きなハードルです。
2025年4月からは育児休業給付金の給付率が手取り換算の100%(28日間)となるので、1ヶ月程度は取得しない理由はないですが、特に6ヶ月以上の育休取得に関しては事前に夫婦で話し合い、経済的な不安は取り除いた状態で育休を取得することが望ましいと思います。
この記事が育休を取得する際の参考になれば幸いです。
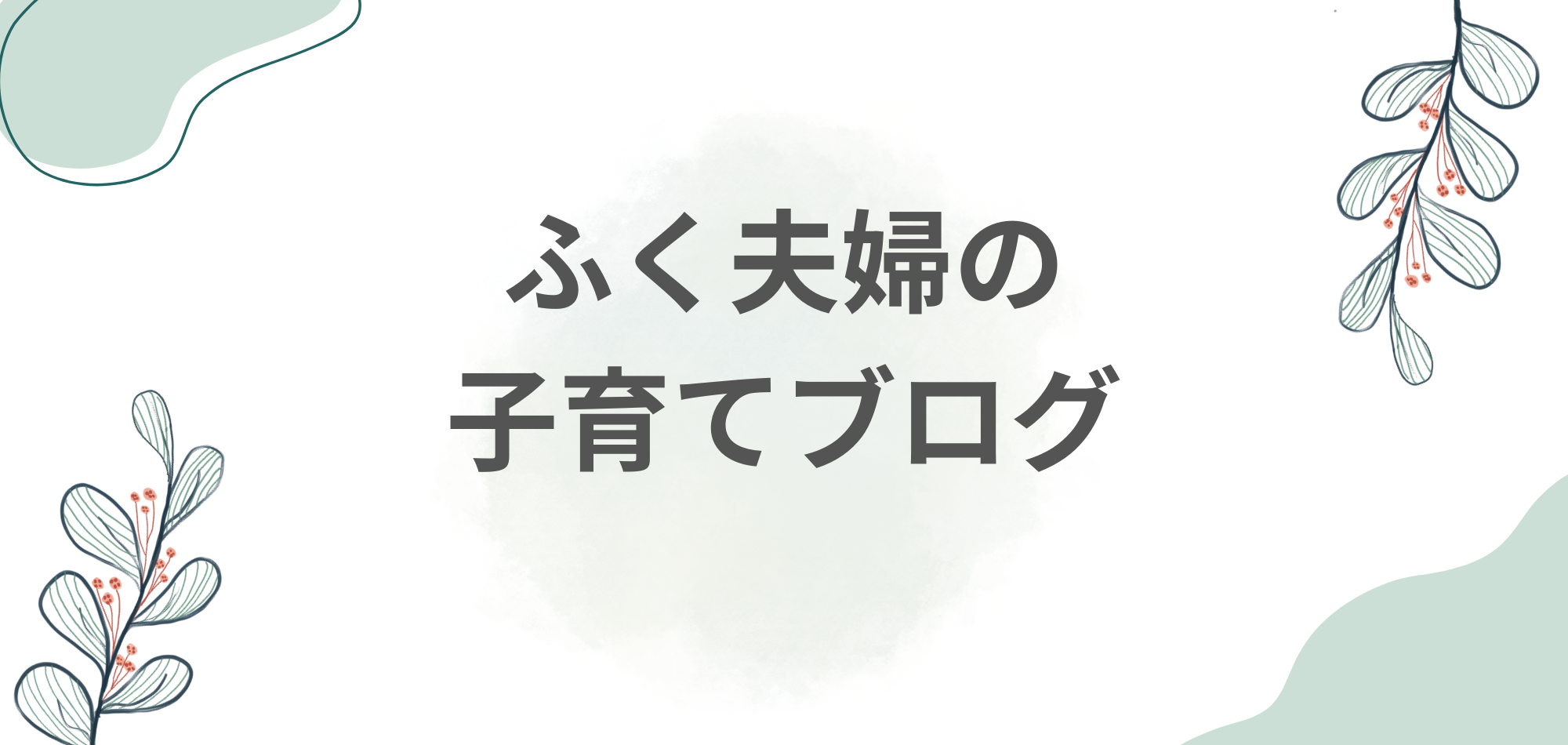
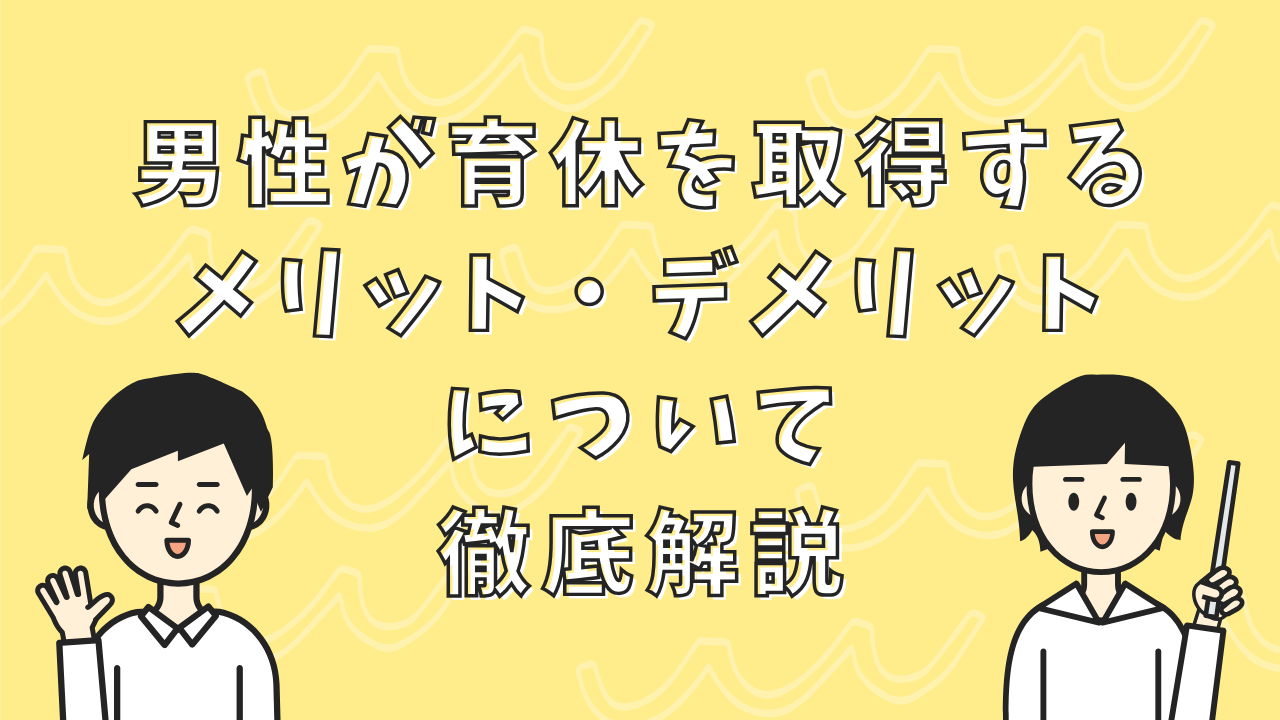
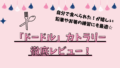
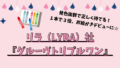
コメント